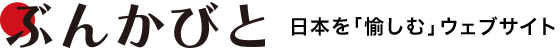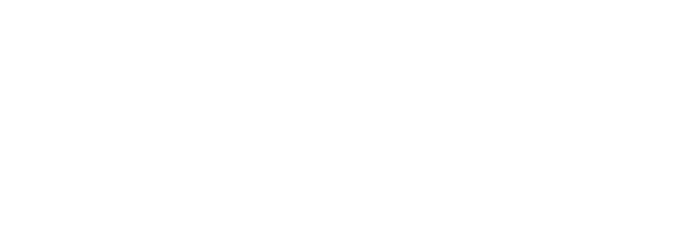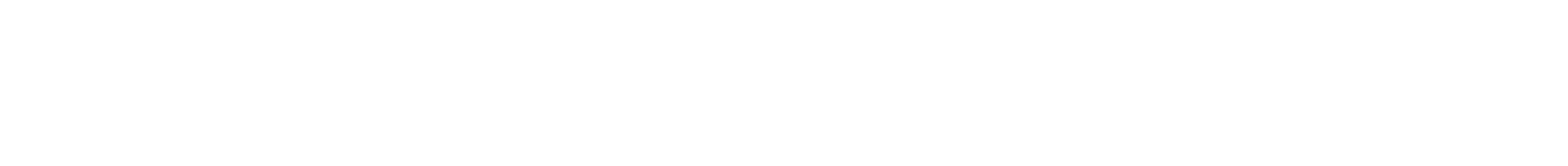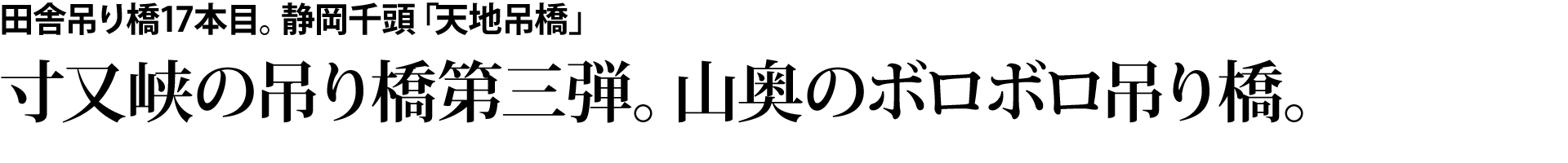猿並橋から遥か先、近づく事すら困難なマイナー吊り橋。
前回紹介した「猿並橋」の先には4本の吊り橋がある。 しかし、ここから先の山は南アルプス深南部。 名前から想像できるように、素人が簡単に入れるような山ではない。 吊り橋へのアクセスは相当に困難で、大げさではなくリアルに命がけである。 猿並橋には「熊出没注意!」の看板があったが、そこから遥か山奥に入って行く訳だから、普通は立ち入る場所ではないのだ。
そんな深い山奥に、嘗ては林業のために造られた吊り橋が何本も存在していた。 しかもその多くがとんでもない高さや長さだったらしく、想像するにとても魅力的な吊り橋だったようだ。 とても残念なことだが、山が深すぎることと、余程ストイックな登山家か渓流釣り師でもない限り人が入らないため、どんどん劣化が進行して崩落し、ワイヤーだけを残して無惨に朽ち果ててしまったようだ。 そんな過酷な環境の中でも、必要なものは修復あるいは架け替えられて残っているのだ。 今回はそんな中の1つ、そんなに目立たないタイプの吊り橋を紹介しよう。
長く危険な道のり。

猿並橋を超えると、突然急勾配の山道を登らされる。 この急勾配は朝日岳を目指す登山道な訳だから当然だ。 少し登ると元々は車道で今は廃道となっている寸又川左岸林道に出る。 ここで朝日岳への登山道とは別れて、延々続くなだらかな上り坂の寸又川左岸林道を北へ歩く。 元々車道なので道幅は広いものの、その道中は落石だらけで驚く程危険。 ガードレールなんかは殆ど落石によって壊れ、崖の下に落ちてしまっている。 更に、場所によっては崖崩れが起きてしまっていて、その崩れた部分を超えて行かなければならないところもあった。

そんな滅多に人が入らない南アルプスの自然の雄大さは半端ではなく、深い山々に囲まれた林道には無数の小さな滝があり、ニホンザルの群れや、ホンシュウジカの他に、天然記念物のニホンカモシカにも出会うことができた。 しかし、もしも出会ったのがツキノワグマだったら・・・・と思うと恐ろしくなる。
延々上り坂の寸又川左岸林道を登って行くと、道が二手に分かれているところに着いた。 ここを左に入ると日向林道で、今度は下り道になる。 日向林道を暫く行くと、遥か下に千頭ダムが見えてきた。ここで長かった林道から別れ、ここからは細い山道を千頭ダムの所まで一気に下ることになる。 この山道の途中には鹿の白骨化した死骸があった。 「ここで熊に襲われたらこうなる運命か・・・」などと考えながら足早に山道を抜ける。

ダムに到着すると、気付かない間に他のモノに襲われていた。 ヤマビルだ! この辺りの山には普通にヤマビルが住んでいるのである。 足早に歩いた筈なのに、靴の中には4匹もヤマビルが入り込んでいて、危うく血を吸われるところだった。
ここからはダム湖に沿って山道を歩く事になるのだが、ここは日向林道とは違って道は細く、ジメジメとしていて落ち葉が降り積もっている。 当然そういう所だからヤマビルが居る。 よーく見ると落ち葉の合間にヤマビルがウネウネと動いていた。 足に着かれないように気をつけながら進むと、小さなトンネルが出現。 流石にこんな不気味なトンネルを抜ける気がしなかったので、迂回して河川敷を歩く。 そして暫く行くと、やっとのことで吊り橋が見えて来た。 既に猿並橋から4時間以上が経過していた。
その名も「天地吊橋」!

やっとのことでたどり着いた吊り橋は、その名も「天地吊橋」。 名前は相当かっこいいのだがこの吊り橋、「夢の吊橋」や「猿並橋」のように観光用にアピールされる訳も無く、当然のことならマイナーな吊り橋だ。 このかっこいい名前の由来は、橋を渡って先に進んだところにある巨大な二本杉の前にある小さなお社「天地の神様」(とは言っても今は崩れて石を積んでいるだけだそうだ)から取っているようだ。 そこには嘗て小さな集落があったのだと言う。 今では跡形も無いが、当時の天地吊橋は生活密着型だったのかも知れない。
天地の神様に登山の安全を祈って、その先の丸盆岳(2066m)を目指す登山道があるらしいのだが、そこ迄のルートは大きく崩れているため危険すぎて近づく人も殆ど居らず、本当にひっそりとしている。 実際、取材中には熟練の登山家が「恐すぎる・・・」と言いながら、天地の神様の手前で諦めて戻って来たところに遭遇した。
この周辺にあった他の吊り橋(登山地図には残っている)は全て崩落してしまって今は存在しない。 それらが存在していた頃は「天地第一吊橋」と呼ばれていたようだ。しかし、マイナー吊り橋などというと地味な感じがするが、ここまで苦労してたどり着いた吊り橋である。 人気吊り橋にはない魅力が多く詰まっているのだ!

予想通りの劣化
ここも大井川水系にある吊り橋の特徴である中心に踏み板を2枚並べるタイプだ。 やはり積雪対策によるものだと思うのだが、地域によってほとんど作りが同じというのが面白い。 「夢の吊橋」も「猿並橋」も、この「天地吊橋」も、構造的にはほぼ同じ造りになっている。 以前、千葉に取材に行った際の吊り橋も、ここ同様に同じ作りの吊り橋が連続して続いたが、吊り橋の地域性も面白いもので、伝統のようなものを感じる。

「夢の吊橋」「猿並橋」と同じ構造とは言え、近づいてみると実状はかなり劣化している。 踏み板を固定している釘は所々外れ、天日にさらされた踏み板は一部反り返って浮いてしまっている。 やはり造りが甘いということではなく、使われないことによる劣化のように見える。 しかし踏み板の上には所々動物の糞が落ちているので、動物は使っているようだ。 更に、針金が一部切れて垂れ下がり、川に着水してしまっているところもある。
しかしこんな痛々しい姿を晒している「天地吊橋」だが、意外なことに歴史はそう古くは無い。 主塔には「平成十一年六月架替」とある。 それでこの劣化な訳だから、自然の厳しさを感じずは居られない。 そしてこの劣化具合が山奥にある吊り橋らしく、なんとも味わい深いのだ。

吊り橋から見える景色はどうだろう。 入り口付近の木々は吊り橋に覆い被さるように生えている。 葉に包まれた所を抜けると、高さもそこそこある。 しっかりした揺れで、危険は感じないのだが、橋の長さと劣化ゆえにかなり揺れる。 前日の雨の影響で少し増水しているため、眼下に広がる川の流れもなかなか激しい・・・。 壊れかけた踏み板は「ギシギシ」と音を立て、渡る者の気持ちを不安にさせる。 そんな踏み板の上をゆっくりと歩をすすめながら、思う存分にスリルを堪能する。
歩みを進めた所から見える、この深い山に囲まれた景観は素晴らしいではないか! こんなに山奥に入っているにも関わらず、これだけ広い川幅を保っているのには驚かされる。 これで川の水が濁っていなければ・・・と悔やまれるが、急な山の斜面に挟まれた寸又川の蛇行する姿は、南アルプスの壮大なスケールを感じさせてくれる。
心して渡るべし!

「夢の吊橋」「猿並橋」と違って「天地吊橋」、「本当に安全か?」という心配もあるので、渡るには覚悟が必要だ。 覚悟を決めたら、「天」を見て「地」を踏みしめ、心して渡るべし!
Vol.16 静岡千頭「猿並橋」 高くて恐くて味わい深い。田舎吊り橋
Vol.18 静岡逆河内「新逆河内吊橋(無想吊橋)」