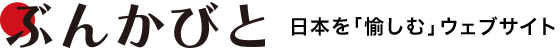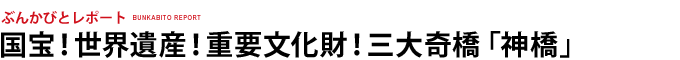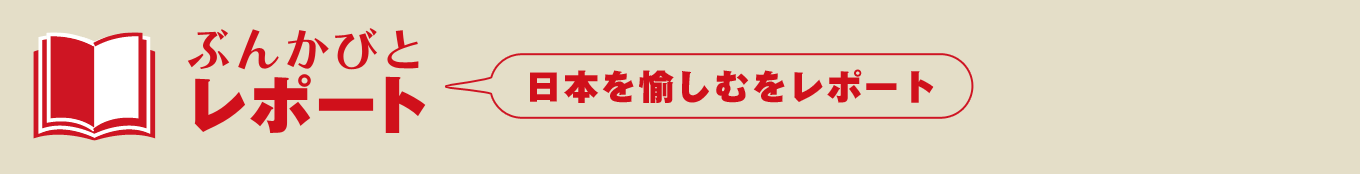
凄い肩書きの持ち主
以前、ぶんかびとレポートで紹介した「猿橋」は「名勝」という肩書きと「日本三大奇橋」と言う肩書きを持っていた。 今回紹介する橋も「日本三大奇橋」に数えられる。 栃木県の日光にある「神橋(しんきょう)」だ。
神橋の持つ肩書きは「名勝」どころの話ではない(名勝も凄いのだが)。 まず、昭和4年に国宝建造物に指定されている。 国宝なのだから、日本国民の宝物という意味である。 そうか、我々の宝物なのだから、それは大切にしなければ。
次に、昭和25年には重要文化財に指定されている。 文化的にも学術的にも重要なものとして国が指定しているのである。 国が認めた重要な橋なのだ。
そして更に、なんと世界遺産にも指定されている! 神橋単体で世界遺産に登録されている訳ではなく、神橋のある日光二荒山神社や日光東照宮が1999年に世界遺産登録された際に、一緒に登録されているのだ。 これはもう、日本の宝だけではなく、人類の宝ということなのだ! すごい・・・。 では、そんな凄い神橋を紹介しよう。

神社でよく見られるような朱色の橋だが、ただならぬ雰囲気を感じる。

巨大な橋脚支えられているが、神橋は猿橋と同様の刎橋(はねばし)だ。

橋の上流の流れは霧がかかっていた。ただならぬ雰囲気の正体はこれだ!
料金を払って入場
神橋を車道側から近づいて眺めるのは無料なのだが、車道は交通量が多いからか大きな柵をしていて入れなくなっている。 向こう岸からは渡れるのだが、渡るには入場料(大人300円、高校生200円、小・中学生100円)が必要。 ここ迄来たら300円をケチっている場合ではない。 ということで、料金を払って入場してみた。

入り口の門の前には靴の泥よけが。国宝で重要文化財で世界遺産で日本三大奇橋だから泥で汚す訳にはいかない。

朱色の門が開いていて、下り坂の先に神橋がある。

近づいてみると迫力がある。

橋の上から大谷川を覗く。水はかなりきれいで、なにより雰囲気が凄い!湿った神橋がまたGOOD!

橋の中央に近代的なステンレスの柵があるのがちょっと残念・・・・・

擬宝珠(ぎぼし)も立派!

車道が近いのもちょっと残念かなぁ
見た目は新しいけど・・・・
一見すると結構新しい感じがしたのだが、それもそのはずで、約10〜20年周期で何度も何度も修復を繰り返しているらしい。 現在のような朱色になったのは1792年以降のことなのだそうだ。 では、最初に神橋が最初に出来た時代を振り返ってみよう。 なんとそれは奈良時代にまで遡る。
神橋の伝説
奈良時代末期、人沙門勝道(日光開山の祖)一行が華厳の滝から流れる大谷川(だいやがわ)の激流に足止めされたとき、神人である深沙大王(神社大王)が右手に赤と青の大蛇を巻いて現れた。 「我は深砂大王である。汝を彼の岸に渡すべし」と二匹の大蛇を放つと、大蛇は絡み合って橋になったという。 一行が渡り終えると橋は消えて無くなっていたが、その後、その場所に丸太で橋を建て「山菅の蛇橋」と読んだのだそうだ。 これが神橋の元となる橋だということである。 猿橋といい、神橋といい、奇妙な伝説が残っているのが面白い。
日光には日光東照宮や華厳の滝など、見所が沢山あるが、ついでに神橋にも立ち寄ってみては如何だろうか。 奈良時代の伝説を想像しながら、国宝で重要文化財で世界遺産で日本三大奇橋の神橋を渡るのも愉しいものだ。
おまけ「なで石」
神橋の入り口のところには「なで石」なるものがある。 気持ちを込めてなでると夢がかなうらしいので、気持ちを込めてなでてみた。
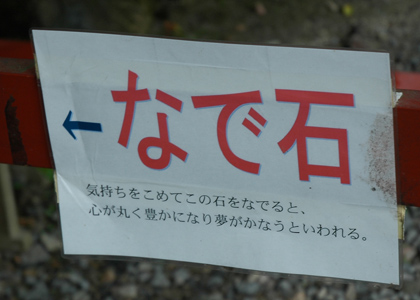
プリントアウトして作られた看板

なんとも言えない形。

心を込めてナデナデ
これで夢は叶うはず。
文/写真:松端秀明